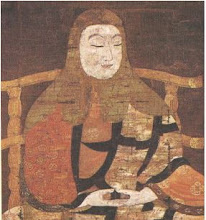久しぶりに故郷に帰ってみた。以前、小学校があったところに大きなビルが建てられているのを見てびっくりした。(成城大・法)
【解答例】The other day I went to my
hometown for the first time in many years, but I was surprised to see there was
a tall building where our elementary school used to be. ―大矢復『最難関大への英作文』(桐原書店), p. 15
大矢は言う。
「久しぶりに訪れた」には過去を表す語句を補う
つまり、
過去形は過去を表す語句と一緒に使うのが原則である。本問では「久しぶりに帰ってみた」のが「いつ?」なのかは書かれていない。しかし、たとえ日本語の問題文になくても、必ず何らかの語句を補うべきである。the other day「先日」、a few days ago「数日前」などが考えられる。
と言うのである。
<必ず何らかの語句を補うべきである>という「べき論」であれば、補わなくてもよいとも言えるのであるから、取り立ててポイントだと言う必要はない。ポイントだと特筆しながら<べきである>としか言わないのは、逃げを打っているようにしか思えない。
<久しぶりに故郷に帰ってみた>のように時を省いた過去をLeechは「不定過去」と呼んでいる。
不定過去を意味する現在完了の場合には特定の時点が表現されないのに対して、単純過去時制を適切に使うには(BEでは)通常過去の明確な基準点(POINT OF ORIENTATION)('then')を表現することが必要である。―G.N.Leech『意味と英語動詞』(大修館書店)、p. 62
問題文は明確な過去時が指定されていないのであるから、Leechに従えば過去形ではなく現在完了形を用いるべきだということになる。
「~してみた」のような言い方はどこか「天声人語」的な感じがしたので調べてみたら、次の文を見付けた。
企業の首脳が、年頭のあいさつで新しい年の抱負や姿勢を明らかにする。どういう演説をしたのだろう、といくつかの演説草稿を改めて読んでみた。
In their New Year addresses to employees, company presidents outlined their aspirations and stands for the coming year. I have gone over the texts of their speeches to see what they said.―『天声人語 ’91春の号』(原書房)、pp. 22-23:1991年1月12日付
「神の国」発言は、森嘉朗首相自身も会員だった「神道政治連盟国会議員懇談会結成30周年記念祝賀会」のあいさつで出た。テープを起こすと、あいさつ全体は400字詰め原稿用紙で訳10枚。あらためて全文を読んでみた。
Prime Minister Yoshiro Mori's controversial statement describing Japan as a "divine country" was made when he addressed a 30th anniversary meeting of a group of Diet members affiliated with the Shito Political League. He had formerly belonged to the group. The transcription of the speech fills about 10 pages of 400-character manuscript paper. I have read the full text.
― 『天声人語 2000夏 vol.121』(原書房)、p. 108:2000年5月26日付
が、現在完了はイギリス英語的である。
完了形のなかでも現在完了形は、会話、手紙、新聞、テレビ・ラジオの報道においてよく使われるが、それでも過去時制が現在完了形の数倍の頻度で用いられる。地域別に見ると、イギリス英語では現在完了形が使われることが多いのに対して、アメリカ英語では過去時制が使われることが多い。―柏野健次『テンスとアスペクトの語法』(開拓社)、p. 156
よって、不定過去の導入文を現在完了形を用いずに過去形で済ませてしまうことも少なくない。
I was prepared to dislike Max Kelada even before I knew him. The war had just finished and the passenger traffic in the ocean-going liners was heary.(私は知り合う前からマックス・ケラダを嫌う用意があった。戦争がちょうど終わり、大洋の連絡客船は満杯だった)―W. Somerset Maughtam, MR KNOW-ALL
解答例を吟味してみよう。まず、I went to my hometownでは「帰る」のニュアンスが出ない。よってI went back to my
hometownないしはI returned to
my hometownのように言うべきである。
それよりもこれでは日本語の「帰ってみた」の「みた」が訳しきれていない。「みた」は無視してよいと判断したのだろうか。訳すとすれば、try ~ingを用いてI tried
returning to my hometown のように言うところか。
次に、日本語が2文になっているのをわざわざ逆接の接続詞butを用いて1文にしているのも気に掛かる。1文にしようとするから、butなのかandなのかを考えなければならなくなるのであって、ここは素直に2文で書けばよいように思われる。
最大の問題はto see there was a tall buildingの部分である。seeの目的語が(ここではthatが省略されているが)that節の場合、seeの意味は対象を「見る」ではなく存在を認識する、つまり「分かる」の意味になってしまう。したがって、ここはthere構文は使わずto see a
tall buildingとすべきである。否、大きなビルは必ずしもノッポとは限らないので、to see a large buildingとすべきであろう。
【池内試訳】I have returned to my hometown
for the first time in many years. I was
surprised to see a large building where the elementary school used to be.
一方、大矢訳を私が採点すると次のようになろう。
The other day I went to my hometown
for the first time in many years, but I was surprised to see
-1(→トル) -1(→went back to) (→years. I)
-1(→トル) -1(→went back to) (→years. I)
there was a tall building where our
elementary school used to be. (7/10点)
-1(→トル)
-1(→トル)
P.S. 直接解答に関係しないが、大矢が第1のポイントとしている部分が引っ掛かった。
「机の上には何があるのだろう?」という質問に対して「1冊の本がある」と伝えたいときは…there is 構文を使う。(p. 14)
大矢は直接例文を挙げていないが、受験英語参考書によく見られる次のような対応関係を考えているのであろう。
What is on the desk? ― There is a book (on the desk).
が、これはよくある誤解である。
「木の下に何がありますか」「大きなベンチがあります」
"What is [×are] under the tree?" "A big bench (is)."(☆(1)この場合、There is a big bench .... は不自然.(2)答えの文のisは《話》では通例省略される / "What is there under the tree?" "There's a big bench."
―グランドセンチュリー和英辞典(三省堂)第2版