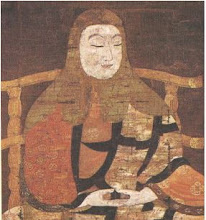91 I was taught at school that the earth ( ) around the sun.
① goes ② went ③ has gone ④ had gone (松山大)
91(①) 時制の一致の例外―不変の真理
訳 私は学校で地球が太陽の周りをまわっていると教わった。
視点➡過去時制 I was taughtに続くthat節の内容は,「地球が太陽の周りを回る」という,
特定の時間に縛られてない「不変の真理」。この場合,動詞の時制は常に現在形となる。
視点➡過去時制 I was taughtに続くthat節の内容は,「地球が太陽の周りを回る」という,
特定の時間に縛られてない「不変の真理」。この場合,動詞の時制は常に現在形となる。
― 小崎充『英文法・語法 標準問題 厳選320題』(旺文社)
日本の受験英語には標記の問題に見られるように、「時制の一致の例外」として、不変の真理は
時制の一致を受けないという「迷信」(superstition)がいまだ根強いように思われる。
時制の一致を受けないという「迷信」(superstition)がいまだ根強いように思われる。
(1) 従節の内容が、一般的真理、現在の習慣、歴史上の事実、比較、仮定などである場合には、主節の動詞が過去時制でも、通例、時制の一致は行われない。
― 安井稔『英文法総覧』(開拓社),p. 293
<通例>と断ってはいるものの、基本的には<時制の一致は行われない>ということである。
おそらくその出所の一つがCurmeの次の解説であろうと推察される。
(2) Sequence of Tenses. In English there is a general rule of sequence when a past indicative
precedes. When the principal proposition has a past indicative, a past tense form must usually
follow: "He wants to do it before his father comes," but "He wanted to do it before his father
came." "He says he will do it sometime," but "He said he would do it sometime." This usage,
though very old, is still for the most part firm. The old sequence, however, is not observed if it
is desired to represent something as habitual, customary, characteristic, or as universally true:
He asked the guard what time the train usually starts. He didn't seem to know that nettles sting.
Columbus proved that the world is round.
― George O. Curme, English Grammar:118
(時制の一致 英語には、過去の直説法が先行する際、一般的な一致の規則がある。主命題が過去の直説法であると、過去時制の形式が通常続かねばならない:「彼は父親が来る(comes)前にそれをやりたがっている」が「彼は父親が来る(came)前にそれをやりたがっていた」。「彼は自分が時々それをやる(will do)と言う」が「彼は自分が時々それをやる(would do)と言った」。この用法は、非常に古いものであるけれども、未だ大部分堅持されている。しかしながら、この古い一致は何かが習慣的、慣習的、特性的ないしは普遍的真理であるとはっきり述べたければ遵守されない:彼はその列車が通常何時に発車するのか車掌に尋ねた。彼はイラクサが刺すのを知らないようだった。コロンブスは世界が丸いことを証明した)(下線池内)
Curmeは「はっきり述べたければ」という条件付で時制の一致は守られないと言っているので
あって、習慣、慣習、特性、普遍的真理は時制が一致しないと言っているのではない。おそらく
はこのことを誤読し「時制の一致の例外」が絶対的なものだと信じ込んでしまったのではないか
と推察される。
あって、習慣、慣習、特性、普遍的真理は時制が一致しないと言っているのではない。おそらく
はこのことを誤読し「時制の一致の例外」が絶対的なものだと信じ込んでしまったのではないか
と推察される。
ところが実際は時制を一致させることが少なくない。イエスペルセンはこれを「心的惰性」(mental inertia)と呼んだ。
(3) the speaker’s mind is moving in the past, and he does not stop to consider
whether each dependent statement refers to one or the other time, but simply
goes on speaking in the tense adapted to the leading idea. In many combinations
it requires a certain effort to use the present tense, even if something is
stated as universally true at all times or as referring to the present moment
in contrast to the time of speaking.
Consequently we cannot expect a rigid system of sequence of tenses to be
always strictly observed.
― Otto Jespersen, A MODERN ENGLISH GRAMMAR ON HISTRICAL PRINCIPLES:11.1(3)
(話し手の心は過去の中で動いており、それぞれの従属節がどの時を述べるのかをゆっくり考えたりせずに、ただ主節に合わせた時制で話し続ける。多くの組み合わせにおいて、たとえ普遍的な真理として述べられたり、話している時と対照的に現在の瞬間を述べているとしても、現在時制を用いるには某かの努力が必要となる。結果として時制の一致という厳格な仕組みがいつも厳密に遵守されるとは思われない)
つまり、たとえ「不変の真理」であっても時制を一致させても構わないということである。
(4) If somebody talked about a situation that has still not changed ― that is to say,
if the original speaker’s present and future are still present and future ― a reporter
can often choose whether to keep the original speaker’s tenses or change them. Both
structures are common.
Direct: The earth goes around the sun.
Indirect: He proved that the earth goes/went around the sun.
― Michael Swan, Practical English Usage, new edition:482:4
(誰かが今でも変わっていない状況について話したとしたら、すなわち、元の発話者の現在や未来が今でも現在や未来であるとしたら、発話者は元の発話者の時制を留めるか変えるかをしばしば選択できる。どちらの構造も一般的である)
(5) The speaker will often use an absolute tense to make clear that he believes
in the truth of the statement.
e.g. The ancient Greeks did not know yet that the earth is/was round.(Is shows that speaker B believes that the earth is round; was is just non-committal: speaker B does not affirm that he believes this(even though he
probably does).)
― Renaat Declerck, A Comprehensive Descriptive Grammar of English, p. 523
(話者は発言が真実であると自分が信じていることを明確にするためによく絶対時制を使う)
(6) 日本では、永遠の真理は、現在時制で述べなければならないと説かれている。
◎Galileo was the first man to realize that the Earth goes round the sun.
[地球は太陽のまわりを回っているということに最初に気付いたのはガリレオだった]
しかし、永遠の真理を表す場合、過去形も正しく、特にthat以下の内容の真偽に関して何らかの疑念(doubt)がある場合、過去形の方が好ましい。
◎The authorities refused to accept that the Earth went round the sun.
[時の権力者は、地球が太陽のまわりを回っているという説を認めなかった]
― G・ワトキンス『続英語を診る』(進学研究社),pp. 140-141
したがって、標記の問題は過去形を用いて
(7) I was taught at school that the earth went around the sun.
として何ら問題がない。
(8) 時制の一致…は規則ではなく1つの傾向として考えておくのがよい。
― 柏野健次編『英語語法レファレンス』(三省堂)、p. 350
時制の一致が絶対的なものでない以上、時制を一致させるかさせないかをテストで問うのはナンセンスである。実際、有名で定評のある大学受験用の英文法・語法問題集を見ても、『Next Stage』(桐原書店)3rd editionや『UPGRADE』(CHART INSTITUTE)改訂版には「時制の一致」の項目すら見られないし、『Vintage』(いいずな書店)も「時制の一致」の一般的な解説があるだけである。
次に、「歴史的事実」における時制の一致を考えてみたい。例えば、
(9) I know that World War II ended in 1945.
を時制の一致でback shiftすれば、
(10) I knew that World War II had ended in 1945.
となろうが、多くの文法書が歴史的事実は大過去形ではなく過去形を用いるとしている。
(11) ex. 先生は生徒たちに「第2次世界大戦は1945年に終わった」と言った.
《直》The teacher said to the pupils, “The Second World War(またはWorld War II)came to an end in 1945.”
《間》The teacher told the pupils that the Second World War came to an end
in 1945.
注意 ... that the Second World War had come ... とするのは誤り.
― 中尾清秋『基礎と演習 英作文』(CHART INSTITUTE),p. 93
が、河上道生氏はこれに異議を唱える。
(12) これは被伝達文の内容が「歴史的事実」である場合の例であるが、この場合も時制の一致に従ってcameをhad comeとすることは決して誤りでない。
― 河上道生・J.D.Monkman『英作文参考書の誤りを正す』(大修館書店),pp. 64-65
さらに次のような指摘もある。
(13) 主節の過去時制に引かれて惰性で時制の一致が行われることもある…歴史的陳述や一般的真理の場合でもこの惰性での時制の一致は見られる。
He said that World War I had broken out in 1914.
My teacher said that two and three made five.
― 柏野健次編『英語語法レファレンス』(三省堂)、p. 351
しかしながら、たとえ大過去形を用いるのが可能だとしても、あまり一般的だとは思われない。が、それは「時制の一致の例外」と言うよりも、一般に大過去形よりも過去形が好まれるからだと言うべきであろう。
(14) 「歴史的事件」についても、学校文法は時制の照応をうけない場合として説明してきたが,それは、時制の照応が生じないというよりも、むしろ、話し手が発話時を基準として(つまり、直示時制を選んで),過去の事件を述べている以上、過去時制は選ばれるべくして選ばれたのだ,と言うべきである.発話時を基準時とする場合は…15世紀の事件であろうと…10年前の事件であろうと、すべて同一の過去時領域に起こったものとして、とらえられるのである。
― 安藤貞雄『現代英文法講義』(開拓社)、p. 697